こんにちは!『Kee(ケエ)【@Kee_s_Art】』です。
今回は「画材を組み合わせた風景・・・絵を描いている風景」をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。
こちらの記事は以下のような方に向けた記事となります!
モノと風景を組み合わせたようなイラストを描いてみたい方
これからペン&水彩でスケッチをしたいと思っている方
絵を描きたいと思っているのに、何から描いていいのか分からずに悩んでいる方
今回のスケッチは、ホームページのトップページや、YouTubeのバナーイラストにも使っているイラストになります。
⬇︎ホームページのトップページ

⬇︎YouTubeのバナーイラスト

絵を描いている人なら家にあるものを組み合わせたらスケッチのモチーフが完成します。
モノ単体だけを描くのもいいけど、モノとモノを組み合わせることで、ちょっとした風景画のようになるので、スケッチの練習にはぴったりだと思います!
なので、今回は画材という絵を描く道具たちを組み合わせたモノを描いてみようと思いました。
スケッチを始めたばかりで、「何から描いていいのか分からない」と思っている人は、今回の紹介するスケッチが参考になりましたら大変嬉しいです。
今回のスケッチもYouTubeにイラストメイキング動画をアップしております。
映像だと、徐々にスケッチが完成していく感じが分かり、より描き方などが伝わると思うので、ご興味のある方は合わせてみてください♪
それではスタートです!
スケッチの参考にしたお写真はこちら
ここで、スケッチの参考にしたお写真を紹介します。

実際に絵を描き始めるところをお写真に撮りました。
手をなしバージョンにするなら、ペン線画のときに実物をみながらでも描けるかなと思います。
ここに出てないもので色塗りをするなら、色塗りも実物を見ながらでもできるのかな?と思いますが・・・
私はこの道具たちを使って色塗りもするので(笑)お写真を見ながらペン線画と色塗りをしました。
スケッチ初心者さんは、今回の私と一緒で複数の絵具を持っているわけではないと思うので、お写真を撮ってスケッチするのがいいかなと思います。
私はいつも実物をスケッチするときも、念のためお写真は撮っておくようにしております!
なので、迷ったらお写真を撮っておくのは、とってもおすすめです◎
ペン線画
それではペンで線画を描いていきます。
今回はラフを描きました。

私の思うラフは「大体この位置にこれ描くよ〜」という目安の線となります。
なので、ラフの線通りにペンで線を描いていくというわけではないので、大雑把でOKです。
それでは、ミリペンを使ってペンで線画を描いていきます。

最初は手から描いていきます。
描き始めるところは、自分が「なんとなく描きたいな〜」っと直感で思ったところから描くのがいいかなと思います。

まっすぐの線のようなところを描くときは、利き手じゃない方の手で、紙を少し浮かした状態にして、紙の後ろから指で線を描くところを支えながら描く・・・、
そうすることで少しばかりは真っ直ぐ描ける気がしております。
今回で言うと、ペンの部分が該当するかなと思います!

手から描き始めたのもあり、ペンと手の線が重ねって描いていってOKです。気にしないで描いていくのがポイントです。
多少の線同士が重ねっているような状態は、失敗しちゃった線とは不思議と感じずに、私の場合だけかもしれませんが、そこまで気にならないかなと思います。
もし、気になったら、あとあと修正液(ホワイト)で消せないいだけなので、気にしないで描いていきましょう。
今回のペンの色は濃い青色のペンなので、線を多く描いても色塗りのときに誤魔化せるので、多めに線を描きました。
手の部分が描き終わったので、スケッチブックを描いていきます。

最初はスケッチブックの枠から描きました。
スケッチブックなので、厚みがあると思います。
なので、枠=四角の右側と下の部分に付け足すような感じで厚みを描くと、スケッチブックっぽくなります。
そして、今回のスケッチブックはリングタイプのスケッチブックとなるので、
紙に当たる部分に小さい四角を描いて、そこにリングを通してあげるように円を描くイメージで追加して描いていきます。

この描いているときのことをあんまり思い出せずに申し訳ないのですが・・・。
リングの数は一応数えてそれっぽい数で描いた気がしております。
だけど、本当の数とずれていても全然OKです。大体あっていればOKのスタンスで描いていきましょう!(笑)
ここで、スケッチブックのお話となったので、今回使っているスケッチブックとペンの紹介をさせていただきます。(急)
スケッチブックは「ohuhu」さんのスケッチブックとなります。
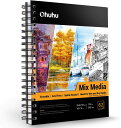
ミリペンはサクラクレパスさんのピグマペンとなります。
ペンを持っている手と、スケッチブックが描き終わったので、水が入っているコップを描きました。

コップの描き方のポイントとしては、まずは上下に丸を描いて、その上下の円を繋げるように縦に線を描くのが簡単に描けるポイントかなと思います。
円柱のイメージでもありますね!円柱を分解して丸と縦線にして考えると書きやすいかもしれません(笑)
筆を拭いたりする用の布巾も、描いていきました。
次に水彩絵具を描いていきます。
紙の向きは、そのままでも大丈夫ですが、今回はなんとなく描きづらいと感じたので、自分が描きやすいと思った向きにして線を描いていきます。

水彩絵具もスケッチブックと基本的には描き方は一緒で、枠から描いていき、細かいところを描いていくスタイルで描き進めていきます。

絵具の四角は、大きさに少しばらつきを感じかもしれませんが、それでOKです。
スケッチの参考にするお写真を見ながら、バランスを見て描いていきます。
水彩絵具が大体描き終わったら、水彩絵具の周りの筆や、水彩ペンも描いていきます。

描くものが少し多いなあと感じるかもしれませんが、
「よく見るとモノを一つずつ描いているだけだ」と思って、頑張って描くっていうのが描き切るためには大事かなと思います。
大枠から描いていき、細かいところを描いていく感じで一つ一つ完成させていきましょう。
全てのものが描き終わったら、明らかに濃い影だなと思う部分は線で描いておきます。

「影の色を少し広範囲に塗るぞ」って思うところ、例えば絵具の下やペンの周り、スケッチブックの厚みの下の部分などは、線で影を塗るところの枠を描いておきました。

これにて、ペン線画が完成しました。
それでは、ラフの線を消して色塗りに入っていきます。
色塗り
色塗りは水彩絵具と水彩ペンを使っていきます。
最初は、水彩絵具を使って塗っていきます。
水彩絵具はウィンザー&ニュートンさんの水彩絵具となります。
影の色の色塗り
まずは、影の色を作って塗っていきます。
使った色は濃い青の「ウルトラマリン」と茶色の「バーントシェンナ」を混ぜた色となります。

ペンを持っている手、その影になっていると感じたところから塗っていきました。
そして、先ほどペン線画のときに「影を広範囲で塗るぞ」と思って線で影の枠を描いたところ・・・スケッチブックの厚みの下のところですね。
こちらに思い切って枠を塗る感じで塗っていきます。
影の色が足りなくなったので、追加で色を作りました。
なんとなく同じ色を目指して作りました。

追加で作った色も先ほど作った影の色と同じ色で、濃い青の「ウルトラマリン」と茶色の「バーントシェンナ」を使って色を作りました。
最初にパレットにのせたウルトラマリンの量が少し少なく感じたので、追加でウルトラマリンを混ぜて、色を調整しながら作っていきました。
それをまだ塗ってないところの影を感じる部分に塗っていきます。

コップの水にも影の色を塗りました。コップの水は、右側、下の方を中心に色を塗ると水っぽくなると思います。
要するに、上の部分は光が反射しているように見えるので、影の色は下の方につけると光と影が表現できるかなと思います。
影の色が大体塗り終わったので、少し先ほどとは違う色の影の色を作っていきたいと思います。
新しく作った影の色は、今塗ってある影の色に塗り重ねていきます。
パレットにある影の色の絵具はほとんど残っておりませんが、こちらのパレットに明るい青の「セルリアンブルー」、黄土色の「イエローオーカー」を混ぜて色を作りました。
試し塗りもしてみましたが、もう少し青みのある色にしたかったので色をさらに追加します。

追加で混ぜた色は、「セルリアンブルー」と茶色の「バーントシェンナ」を混ぜました。

青の割合が多くなった色が作れたかなと思います。
少しくすみを感じるような青の色が作りたかったので、よかったです。
コップの色に塗っていきます。

コップの色はもともと最初に塗った影の色が塗ってあるけど、上から重ねて塗っていって、全然OKです。
今コップの色を塗った色がまだパレットに残っているので、そこにさらに濃い青の「ウルトラマリン」を混ぜて色を作りました。
その色を筆を拭く用の布巾の色に塗り重ねていきます。

布巾の色はグレーだけど、少し青みを感じるグレーだったのもあり、少し青みを追加しました。
コップや布巾の色は、最初に塗った影の色のグレーだけでもOKな部分ではありますが、少しだけでも色を変えてあげることで、一つ一つのモノとして際立ったかなと思います。

色を感じるところの色塗り
影の色が塗り終わったので、ここからは色を感じるところに色を塗っていきます。
パレットに残っている青っぽいグレーがあったところに、さらに青の「ウルトラマリン」を足して色を作っていきます。
試し塗りで濃いめの青となっていることを確認しました。

こちらでペンの色の青い部分を塗っていきます。

青い部分が塗り終わったら、ペンのキャップの金属の部分を塗っていきます。
明るい黄色の「レモンイエロー」と黄土色の「イエローオーカー」を混ぜて色を作りました。

金属系の色は色を作るのが難しいかなと思うのですが、
実物よりも黄色みが強いというか、鮮やかな色で塗っても馴染むと思います。

キャップの下の方・・・紙に挟む部分ですね。
こちらは色が少し影になっているので、少し色を変えて塗ります。

塗った色は、今作った黄色の色にパレットに残っている青を少し混ぜた色となります。
そうすることで、ほんの少し色にくすみが出て、影の色が混じったような印象になるかなと思います。
ペンが塗り終わったので、次は手の色を塗っていきたいと思います。
まずは爪の色から塗っていきます。
使った色は赤オレンジのような色の「カドミウムレッド」、そこに白の「チャイニーズホワイト」を多めに混ぜた色となります。

爪が塗り終わったら、水の量を多めにして手全体にも塗っていきます。
水の量を変えるだけでも色の変化を出すことができるのが水彩絵具の色塗りの面白いところだと思います。

手が塗り終わったので、続いて、画材の色を塗っていきます。
先ほど、ペンのキャップを塗った色がパレットに残っているので、
まずはその色を使って筆の毛の部分、その後ろにある金属の部分を塗っていきます。

筆の毛の先はもう少し茶色にしたかったので、少し茶色の「バーントシェンナ」を混ぜて、茶色っぽい色を作り、塗っていきました。

毛と金属の部分の色に変化が出たことで、より筆ということがわかる絵になったかなと思います。
筆の先が塗り終わったので、次に筆の持つところを塗っていきます。
筆の持つところは明るい青を感じるので、ダイレクトに明るい青の「セルリアンブルー」を新たにパレットにとりました。
それを塗っていきます。
鮮やかな色を塗りたいときは、絵具をそのままの色で塗ると鮮やかさを感じる色になるので、おすすめです。

次に水彩ペンを塗っていきます。
水彩ペンの先の部分はダイレクトにその色の水彩ペンで塗っていきます。
ちなみに水彩ペンは呉竹さんの「ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ」となります。
明るい茶色の水彩ペンは「No.067 MUSTARD」となります。

真ん中の王道の黄色の水彩ペンは「No.050 YELLOW」となります。

そして3本目の水彩ペンは茶色とグレーが混じったような色の「No.096 MID GRAY」となります。

水彩ペンの筆の先端は濃いめに、その下の色の部分は水をつけて少し薄めの色で塗って、微々たる色の違いを表現しました。
続いて、水彩ペンの下のホワイトペンの色を塗っていきます。
ホワイトだから色を塗らなくてもOKな部分だと思いますが、ホワイトといえど少し色を感じるので塗っていきます。
何も色がないパレットのところに、白の「チャイニーズホワイト」、そこにもともとパレットにある黄色の絵具をほんの少し混ぜました。

クリーム色のような色となるので、少し温かみのある印象を作ることができたと思います。
続いて、水彩絵具を塗っていきます。
水彩絵具は水彩ペンのペン先の部分と一緒で、該当する色のそのものをダイレクトに塗っていきます。

絵具の色をそのまま塗ることで、色見本みたいな役割にもなるかなと思います。
水彩絵具の色見本を作りたいな〜って考えている人は、画材をスケッチしてみるのは、そういった意味でもおすすめです。


水彩絵具の色が塗り終わりました。
画材が塗り終わって全体を見てみると、マスタードの水彩ペンの色が薄いと感じたので、追加で色を足しました。

画材の色が塗られたのもあり、もう少し手の肌色を濃くした方がバランスがいいと思ったので、肌色の水彩ペンを使って色味を調整していきます。

使った水彩ペンは「No.071 NATURAL BEIGE」となります。
最後にコップの水の部分、青の絵具を追加して水っぽさを表現しました。

これにて色塗りが完成です!
スケッチ完成
色塗りも無事に完成し、スケッチが完成しました!


今回は影の色をうまく活かしながら、色塗りができたかなと思っております。
そして、複数の画材・・・イコール複数のモノたちを組み合わせることによって、一種の風景画を描くことができました。
今回のスケッチの描き方をより詳しく知りたい方は、ぜひYouTubeの動画も見てください!
今回のスケッチで使った道具紹介
記事の中でも紹介もさせていただきましたが、最後に今回のスケッチで使った道具たちをさっと紹介します。
紙はohuhuさんのスケッチブックとなります。
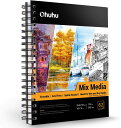
ペン線画に使ったペンはサクラクレパスさんのピグマペンとなります。
色塗りに使った水彩絵具は、ウィンザー&ニュートンさんの水彩絵具です。
水彩ペンは呉竹さんの「ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ」となります。
これからペン&水彩でスケッチを描いてみたい方の参考になりましたら嬉しいです!
そして、以下の動画では、水彩スケッチをこれから始めてみたい方に向けて、描き方のほかに画材についても詳しく紹介しております。気になった方は見てください♪
『【スケッチの練習】何を描いていいかわからない人向け!画材を組み合わせたような風景画を描いてみよう!』のおわりに。
今回は「画材を組み合わせた風景・・・絵を描いている風景」のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。
風景画とはよく見ると、モノとモノの集合体となります。
なので、風景画を描きたいと思っているスケッチ初心者さんは、まずはモノを一つ描いてみる、それから二つモノを描くのように徐々に増やしていくっていうのが絵の練習なると思います。
なので、画材をスケッチしてみるのはおすすめです。
そして、今回紹介した私の描き方が参考になりましたら、大変嬉しいなと思っております。
ブログ&YouTubeでは、こんな感じで私のスケッチを発信をしております。
これからの発信にも興味を持っていただけましたら、またサイトに遊びにきてください。
YouTubeのチャンネル登録も良かったらお願いします!
自分ペースの更新となりますがXやnoteもやっておりますので、良かったらこちらもフォローお願いします。
描いて欲しいものとか、話して欲しいお話などありましたら、YouTubeのコメントまたは本サイトのお問い合わせから教えてください♪
それでは今回は終わりです。またね
当ブログは著作権法を遵守し、第三者の権利を侵害しないよう努めています。










